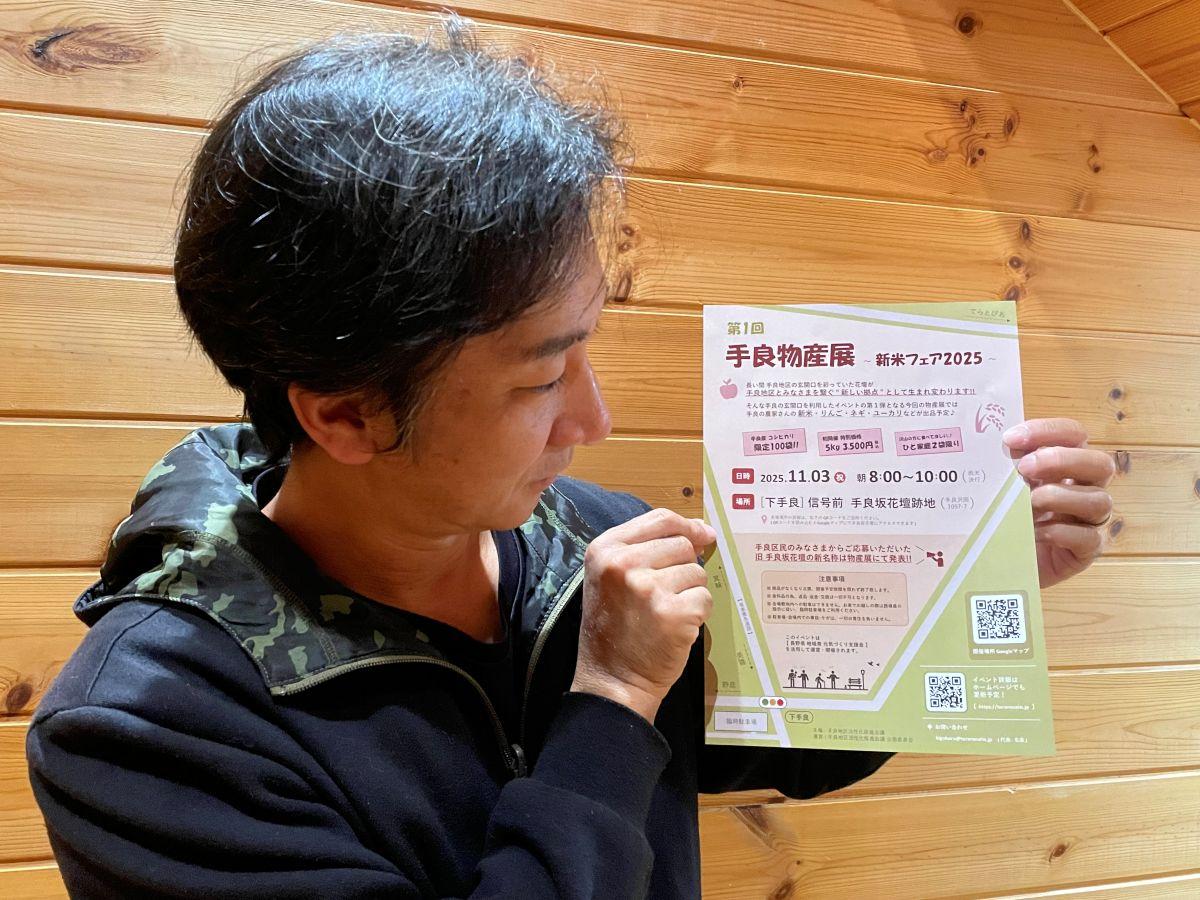伊那市役所で「市民のつどい」 「理解し合い支え合う地域社会」をテーマに

男女共同参画社会を目指す「伊那市民のつどい」が11月15日、伊那市役所1階・多目的ホールで開かれ、40人を超える市民が参加した。
例年、男女共同参画やジェンダーの視点を中心にした講演会などを行ってきたが、今年は「理解し合い支え合う地域社会~多文化共生の視点から~」をテーマに、国籍や文化、背景の違いを持つ人々が暮らす地域社会のあり方を市民と共に考える機会とした。
講師を務めたのは、伊那市集落支援員として多文化共生推進に取り組む宮ケ迫ナンシー理沙さん。戦後の日本では人口増加や食糧難が深刻化し、政府は海外移住を促進。ブラジルへは約26万人が渡ったとされ、その中に宮ケ迫さんの祖父母や両親も含まれていた。宮ケ迫さんはブラジルで生まれ、戸籍上は2世に当たるが、「祖父母の意思による移民としての歴史と、自分の立ち位置を考えると、気持ちのうえでは『2.5世』に近い」と話す。講演では、外国籍の子どもたちの学習支援、震災時に国際移住機関(IOM)で外国人相談員として従事した経験、ブラジルの邦字新聞記者としての活動など、多文化と向き合ってきたこれまでの歩みを紹介。「多文化共生とは、互いの違いを理解し、対等な関係を築こうとする姿勢である」と伝えた。
会場では、参加者が『特権』を体感するワークも行った。新聞紙で作ったボールを会場前方の箱へ、各自の席から投げ入れるもの。座席は6列ほどに並び、前列の参加者は容易に入れられる一方、後方に行くほど箱の位置が見えにくくなり、狙うことすら難しくなる。宮ケ迫さんは「前にいる人は、自分が恵まれた位置にいると気づきにくい。でも後ろの人はやってみて初めて『不公平さ』を感じる。マジョリティーとマイノリティーの差を埋めるには、自身が持っている特権を、それぞれが認識することが大切」と説明した。
講演ではさらに、伊那市に暮らす外国籍住民の現状についても紹介。ブラジル、フィリピン、中国、ベトナムなど多様なルーツを持つ人々が地域に生活していることに触れ、「地域で暮らし働く外国人住民の方々も、日々の生活や仕事、地域活動などさまざまな形で地域を支えていく一員。誰もが同じスタートラインに立ち、それぞれが自分らしく生きられるような仕組みが当たり前に整っていくことで、より暮らしやすい地域になることを願っている」と話した。
伊那市在住の30代女性は「多様性という言葉を普段から耳にしても、どういう形が多様性のある社会なのか現実味がなかった。今回の話が良い機会となった」と振り返る。