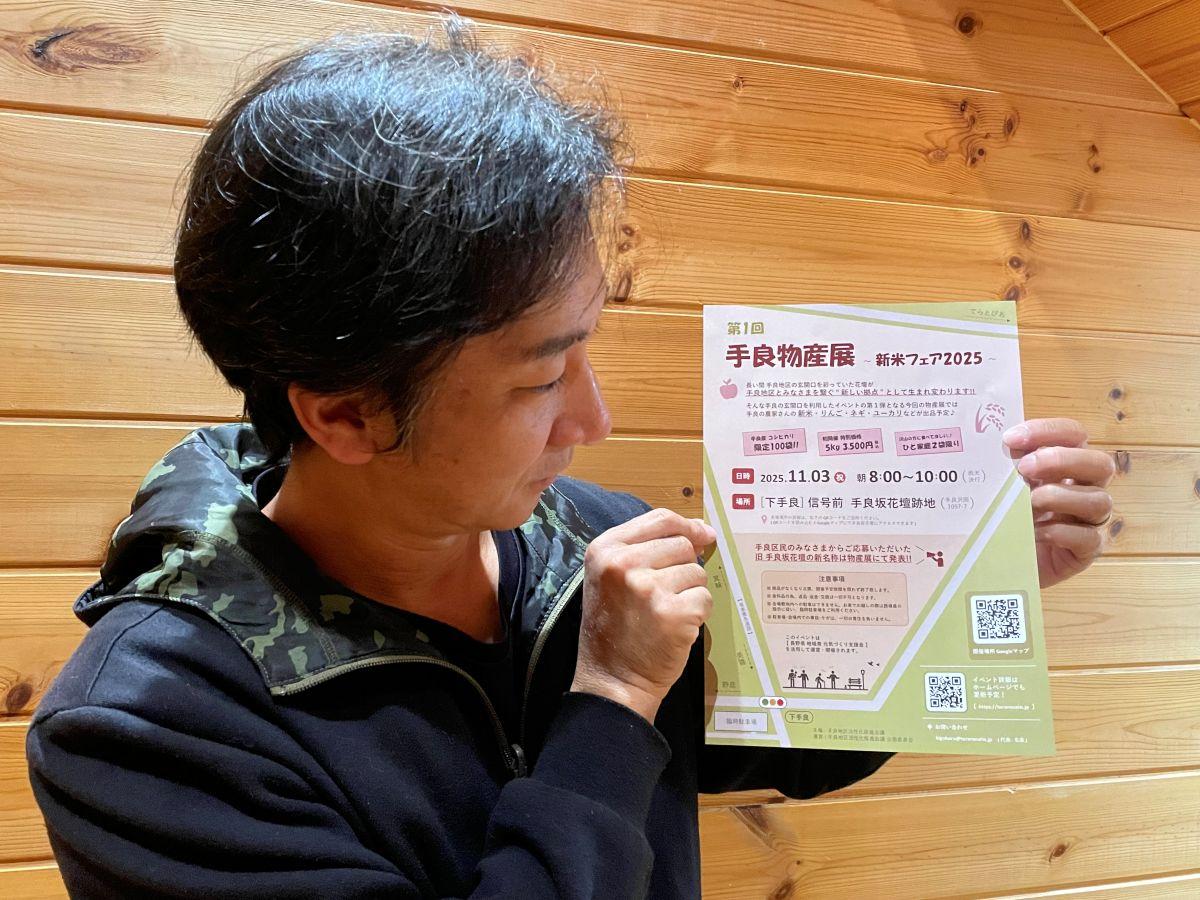働く女性3人が田んぼをシェアして米作りに初挑戦 「おかげさ米」報告会

米作りに初挑戦した箕輪町在住・在勤の女性3人が11月12日、「米作り報告会」を箕輪町文化センター(箕輪町松島)で開催した。
3人は同町議会議員の中野友美さん、会社員の小野まゆみさん、同町地域おこし協力隊員の山野邉智美さん。報告会では実際に収穫した精米したての新米で作ったおにぎりを提供し、これまでの苦労、喜びや課題などを参加者と共有した。昼と夜の部で、合わせて50人近くの人が足を運んだ。
「仕事と両立しながら、安心・安全な米を作りたい」という思いから、農薬を使わず・無堆肥での栽培を目指し、取り入れたのは「紙マルチ」を使った田植え方法。黒い紙マルチの上に苗を植えることで太陽の光を遮断し雑草の繁殖を抑え、除草の手間と除草剤を省くことができたという。一方、紙マルチ購入にかかる費用も9アールで約3万円と安くはなかったという。中野さんは「紙マルチが微生物に分解されるまでの約40日間、本当に雑草は生えなかった。おかげで除草のために時間と労力を割くことがなく、働く私たちにとっては大きなメリット。かかった費用も3人で分担できるため、特に負担だとは感じなかった」と振り返る。
代(しろ)かきや、稲刈り、稲の乾燥など農業機械を使う作業工程については地元事業者に委託し、全ての出費は16万円余りだったことも報告。中野さんは「初めての挑戦で分からないことだらけで無駄な工程が発生したり、必要な道具も購入したりと初年度ゆえに費用もかさんだが、3家族が1年間食べられるだけの収量に当たる285キロを確保できた」と話す。
稲が育つ過程ではカビが原因で稲が枯れ、収量減少の要因にもなる「イネいもち病」の発生やイネツトムシによる食害被害にも見舞われたことも報告。適切な苗間を確保せずに密に苗を密に植えたことが主な原因ということも分かった。病気を止める薬を購入して対策を講じると同時に、動噴散布機を購入して食酢を300倍に薄め散布し、広がらないよう予防するなどして見守ったという。
メンバーの小野さんは「米作りにおいては全くの素人故に、多くの人の力を借りての米作りとなった。たくさんの人のおかげでできた米ということで『おかげさ米(まい)』と名付けた」と話し、「水管理をしてくれたり、稲の様子を見て病気を教えてくれたり、これまでつながることのなかった地域の方と米作りを通じてつながり、たくさんの人の温かさに触れた。農家さんへの感謝と尊敬の念を改めて強くした」とも。「来年以降はどうするのか」と参加者から問われると、「今後も試行錯誤を重ねながら、自分たちでできることを増やしたい。多忙な共働き家庭でも持続可能な米作りの方法を探り、米作りや農業が次世代につながっていくよう挑戦してきたい」と回答し、意気込みを見せていた。