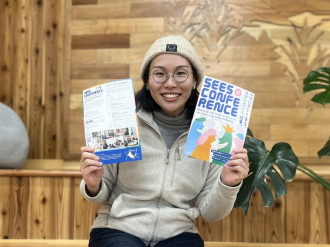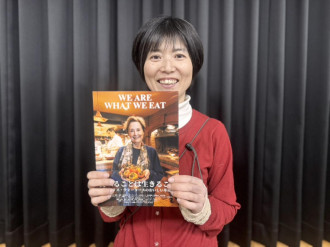伊那で信州大農学部創立80周年記念プレイベント 地域密着の研究発表

信州大学農学部創立80周年記念のプレイベント「地域と連携する農学部~伊那谷の歴史に関わり発展に寄与する研究~」が5月18日、伊那市産学官連携拠点施設「INADANI SEES(イナダニシーズ)」(伊那市西箕輪)で開催され、70人が参加した。
主催は同大農学部同窓会。同大農学部が来年で創立80周年を迎えるに当たり企画されたプレイベント。シンポジウムの司会・コーディネーターには伊那市創造館館長の捧(ささげ)剛太さんを迎え、同大農学部名誉教授の辻井弘忠さん、井上直人さん、同部教授の松島憲一さん、同部助教の三木敦朗さんが登壇した。
シンポジウムで、辻井さんは「木曽馬のお話」をテーマに伊那街道の発達と木曽馬の利用方法や木曽馬の特徴、現在の古墳の数との関係について述べた。井上さんは「高遠そばとの関わり」をテーマに、在来そばの特徴や農家・そば店・行政・大学で連携し研究した高遠そばについて発表。「在来種の保存のためには、住民に在来種に関する思い入れが重要であり、住民参加型の育種・栽培・採取システムの構造を維持する必要がある」と井上さん。
松島さんは「信州の伝統野菜の唐辛子」をテーマに、伝統野菜について説明。伝統野菜は、化学的、文化的、経済的に有効であり地域の食文化として残しておく必要があるとしたうえで、信州のトウガラシ在来品種とその地域で昔から食べられている料理について紹介した。三木さんは「伊那谷の新たな林業」をテーマに、島崎洋路の「山造りは不可能な事柄ではなく、やればできる営みである」という言葉を紹介。現在、世の中と森林のニーズの変化を背景に、行政は大規模林業の普及を進めているが、小さい林業経営の普及の重要性や可能性に触れた。
司会・コーディネーターの捧さんは「辻井さんの話を聞いて木曽馬が犬や猫のようなもっと身近な存在になればいいなと思った。井上さんの高遠そばの発表では、地域の人の思いは、新しい文化を作ることも、昔の文化を守ることもできると感じた。松島さんの発表で信州在来品種のトウガラシを知り、今に伝わる昔ながらの食べ方でご飯3杯はいける。三木さんの話から伊那という場所が地域と森と生きていける素晴らしい場所であることを再認識した」と感想を述べた。
質疑応答では、同大農学部構内の森林ついて、「森林と人間の営みが感じられない」という指摘や、「大学内の森林空間を利用できない状況であり、大学での学びや研究による知見や成果を地域の人が得ることができる場所が欲しい」という参加者からの声も聞かれた。
捧さんは「登壇してくれた4人の研究はどれも興味深く、地域と密着した研究をされていた。プレイベントでは限られた時間の中での発表だったので、来年の80周年イベントに向けて、もっといろいろと聞ける場がこれからもあるとうれしい。一過性のものではなく、地域に還元でき未来につながるようなきっかけになれば」と期待を込める。