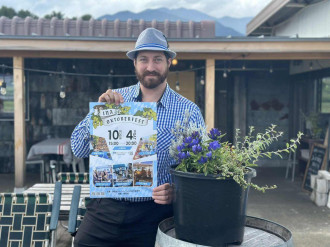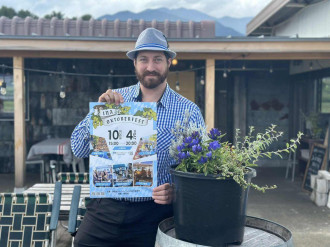駒ケ根で「大宮五十鈴神社例祭」 火の粉が振り注ぐ「三国煙火」も

大宮五十鈴神社(駒ケ根市赤穂)で9月23日・24日、「大宮五十鈴神社例祭」が行われる。
毎年9月下旬の秋分の日に行われる同祭は、同神社が1907(明治40)年から1908(明治41)年にかけての「神社合祀(ごうし)令」により、上穂村各村落に古くから祭られていた神社8社を合祀(ごうし)して「大宮五十鈴神社」と称した頃より続く祭り。23日の「宵祭り」では「獅子練り」や目玉となる「三国煙火」などが行われ、翌24日は関係者のみで「例祭」を行う。
23日の朝8時ごろから行う「獅子練り」は、「おかめ」「ひょっとこ」「てんぐ」「白狐(びゃっこ)」に変装した市民が市内を練り歩く。練り歩きが終わる14時ごろから同社で獅子の頭を切り落とす「獅子切り」を行い奉納すると、「宵祭り」の神事が始まる。同社宮司の白鳥俊明さんは「ここの地域では獅子は災いをもたらすと伝えられており、獅子練りで練り歩くことで獅子が厄を受け、その後、首切りをすることで厄落としになるという意味がある」と話す。
同日18時30分から「初三国一煙火」、20時30分から「大三国一煙火」を行う。境内に設置された地上8メートルの櫓(やぐら)から滝のように降り注ぐ火の粉の下で、腹掛け姿の氏子たちが「わっしょい、わっしょい」と叫びながら「おんべ」や「纏(まとい)」を振りかざす「三国煙火」は同祭見どころの一つとなっている。
白鳥さんは「三国煙火は降り注ぐ火の粉が圧巻。火の粉が掛かると服に穴が空く可能性があるので一張羅でないものをお勧めする。コロナ禍以降はイベントなども縮小し寂しくなってしまったが、少しずつコロナ禍前の活気を取り戻してきたい」と話す。